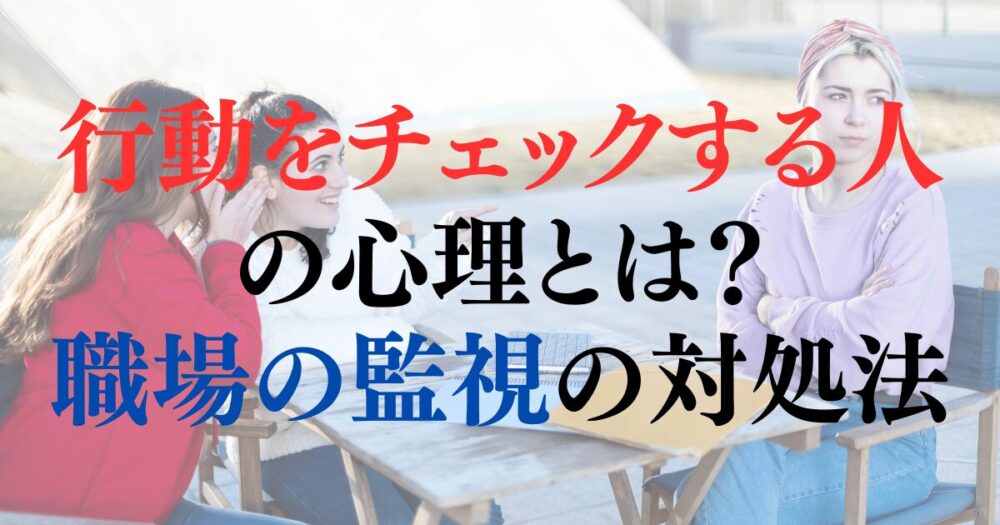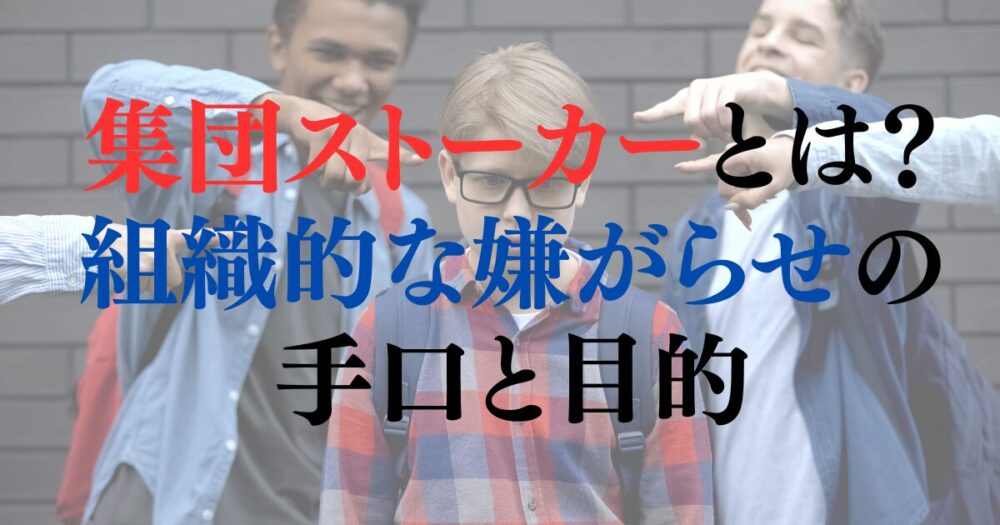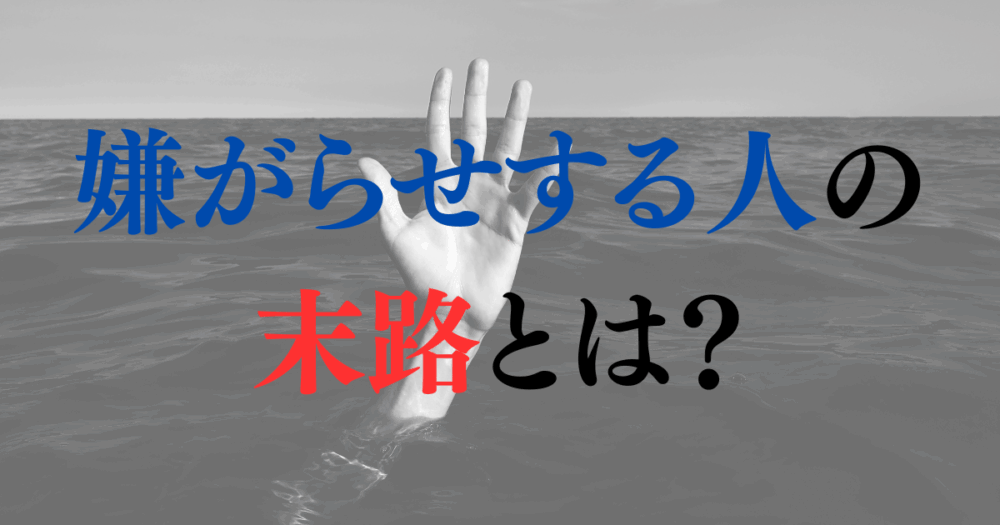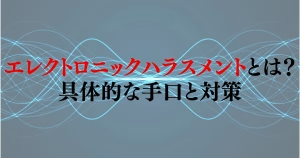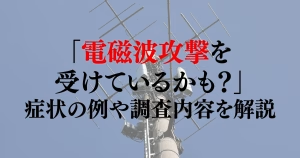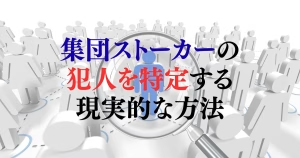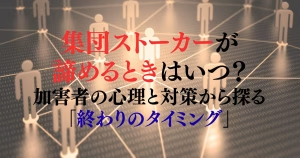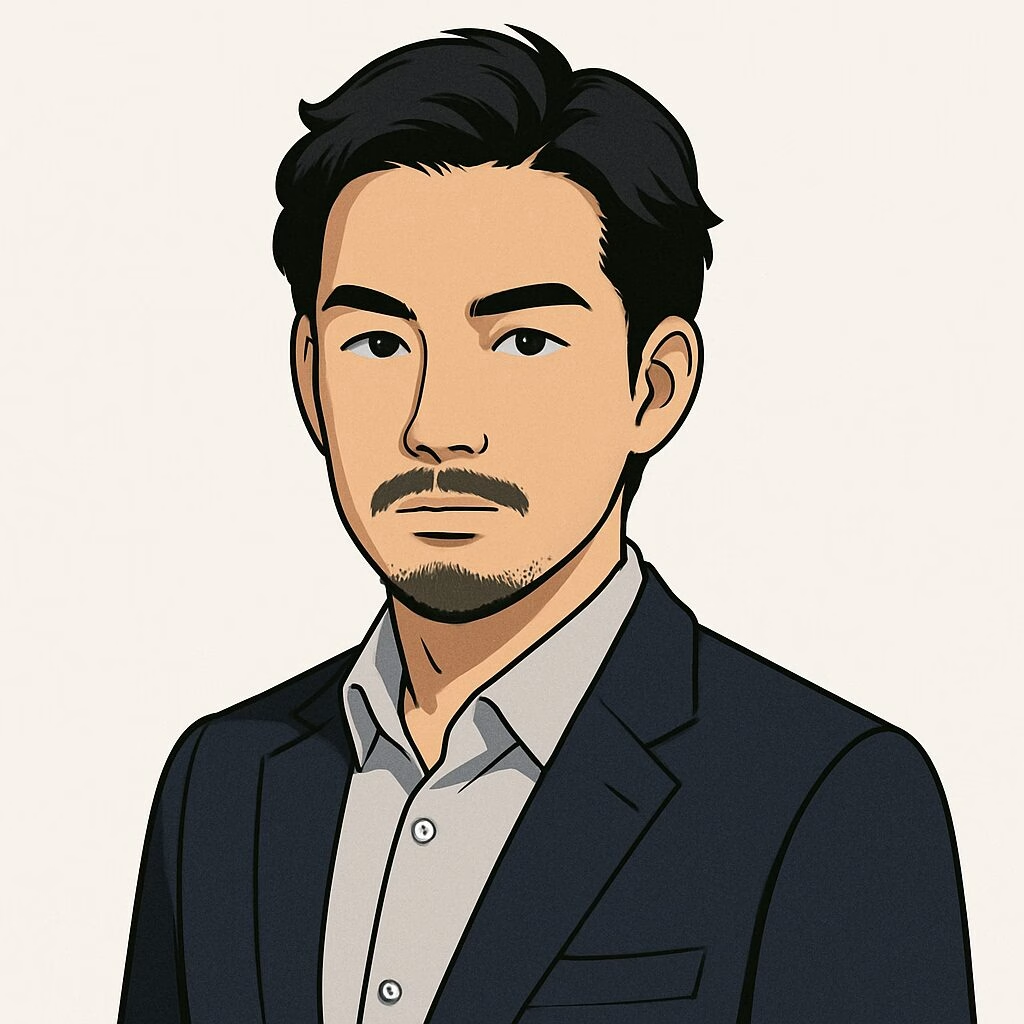上司の嫌がらせへの対処法とは?よくある事例や考えられる原因も紹介
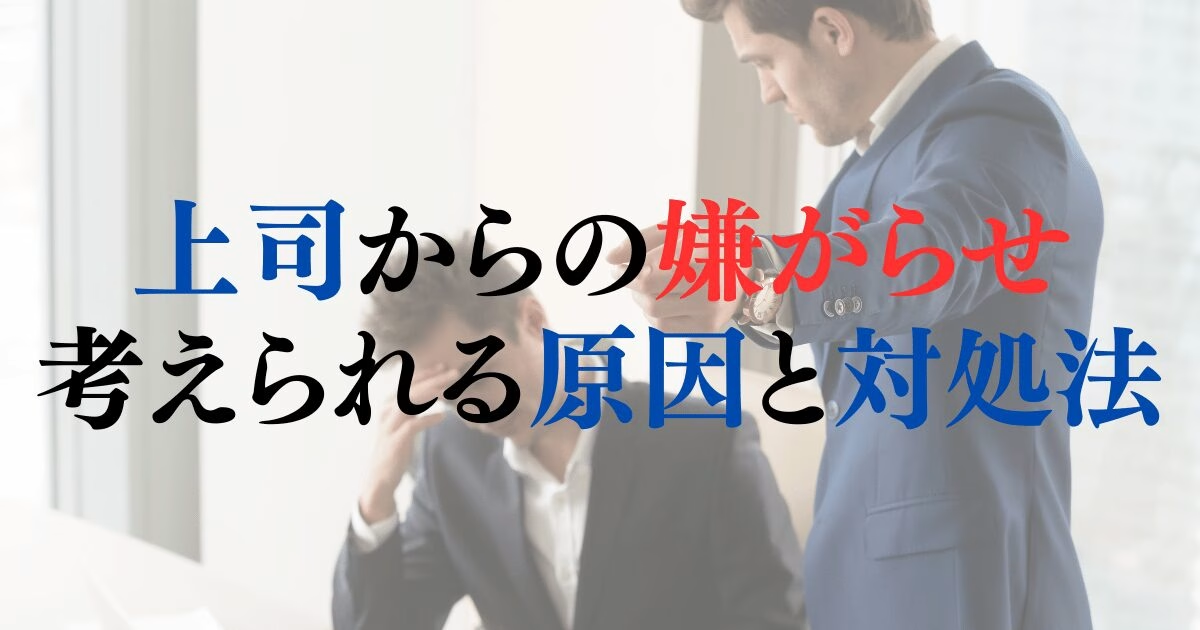
理不尽な業務指示やハラスメントなど、上司による様々な嫌がらせに悩んでいませんか?
上司による嫌がらせは、本人そのものの特性や仕事への価値観に起因するものまで様々です。
本記事では、上司の嫌がらせでよくある事例や原因を紹介します。
上司による嫌がらせが起こる心理的要因も解説しています。
上司の心理を理解して、適切な対処をしていきましょう。
上司の嫌がらせでよくある事例|該当するものをチェック
上司の嫌がらせでよくあるパターンは、主に下記9つです。
- 執拗に幼稚な嫌がらせをしてくる
- ハラスメント行為をしてくる
- 大勢の前で批判・暴言を浴びせてくる
- 無視や仲間はずれをしてくる
- 他社員に悪い噂を流す
- 過多な業務を押し付けてくる
- 休みを取りづらくしてくる
- 故意に仕事を与えない
- プライベートの領域に踏み込んでくる
それぞれに該当する具体的な行為も解説します。
自分が受けている嫌がらせと同様の行為はないか確認しましょう。
執拗に幼稚な嫌がらせをしてくる
上司の嫌がらせでよくある事例として、まず挙げられるのが幼稚な嫌がらせです。
机や椅子を勝手に動かしたり、持ち物を隠したりといった子どものイジメような行為が該当します。
場合によっては、何度注意しても聞かずイタズラ感覚で執拗に嫌がらせを続けてくるパターンもあり得ます。
例えそれが幼稚な嫌がらせでも、内容の「しょうもなさ」により周りに相談しにくいケースも少なくありません。
「自分が気にしすぎなのでは」と思い込むことで、余計なストレスを溜めないよう注意しましょう。
関連記事:職場で「幼稚な嫌がらせ」がストレス…|相手にしないべき?対処法まとめ
ハラスメント行為をしてくる
上司の嫌がらせには、下記3つの「ハラスメント」に該当する内容も多く見られます。
| ハラスメントの種類 | 意味 | 具体例 |
| パワハラ | 職場での地位や権限を利用して、部下に精神的・肉体的な苦痛を与える行為 | わざと大勢の前で罵倒する 過剰な業務を押し付ける 成果を認めず過小評価する |
| セクハラ | 性的な内容を含む言動によって相手を不快にさせる行為 | 過度なボディタッチをしてくる 下ネタを繰り返してくる プライベートや結婚についてしつこく詮索する |
| モラハラ | 侮辱的な言葉や態度によって相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為 | 仲間外れにする根拠のない噂を流す 人格を否定するような発言を繰り返す |
嫌がらせの内容によっては、複数のハラスメントが含まれるケースもあります。
大勢の前で批判・暴言を浴びせてくる
上司の中には、人前でわざと大きな声で批判・暴言を浴びせてくる人もいます。
会議や朝礼の場で、特定の相手に向かって「お前はダメだ」「こんな簡単なこともできないのか」と罵る行為が該当します。
このパターンの嫌がらせは、エスカレートすると人格否定や誹謗中傷に繋がりかねません。
嫌がらせの延長で人前での罵倒を繰り返してくる上司の場合、立派なハラスメントである可能性が濃厚です。
無視や仲間はずれをしてくる
話しかけても無視したり、仲間はずれにしたりといった嫌がらせをしてくる上司もいます。
近年多いのは、重要な会議や懇親会に特定の人をわざと呼ばず、後で本人の聞こえる場所で楽しそうに当時の話題を語るパターンです。
周囲も上司に意見できず、対象人物に話しかけづらい雰囲気が広がり、より一層孤立してしまうという負のループが発生します。
ケースによっては、部署間の連携や業務の進捗に支障が出かねません。
上司による意図的な無視や仲間はずれは、職場での社会的排除という重大な嫌がらせにあたります。
他社員に悪い噂を流す
他の社員に悪い噂を流し、イメージを下げてくる上司も一定数存在します。
職場内の噂は瞬く間に広がるため、長期的な人間関係や評価に悪影響を及ぼしかねません。
特に上司がありもしない噂を流す「虚言癖」がある人の場合は、注意が必要です。
たとえ事実に基づいた内容の悪い噂でも、話が盛られていないかチェックしましょう。
内容の悪質さによっては、嫌がらせではなく名誉毀損にあたる可能性もあります。
過多な業務を押し付けてくる
嫌がらせの一環として、あまりにも多すぎる仕事を押し付けてくる上司もいます。
同意なしに他社員の仕事を割り振ったり、無理な納期を設定して残業を強いてきたりする行為は、嫌がらせでなくハラスメントです。
特に口達者な上司の場合、甘い言葉を交えて限界まで部下を働かせようとします。
結果的に過労やストレスの原因となり、かえって仕事のパフォーマンスを悪化させてしまうケースも少なくありません。
自分の仕事量「だけ」が不自然に多いと感じたら、上司によるパワハラも疑いましょう。
休みを取りづらくしてくる
嫌がらせ目的で休みや有給を取りづらくし、精神的なダメージを与えてくる上司もいます。
「繁忙期なのに休むのか」「他の人に迷惑がかかる」といった言葉をかけ、休みを取らせない行為はパワハラそのものです。
本来、有給取得は労働者の権利であり、上司が勝手にルールを決めてよいものではありません。
何度交渉しても休みを取らせてもらえない場合、社内の窓口や労基(労働基準監督署)への相談も検討しましょう。
故意に仕事を与えない
嫌がらせの一環として、わざと仕事を与えてこない上司もいます。
過度な業務を押し付けるとは反対に、仕事のない時間を故意に増やして自己肯定感を低下させるといった嫌がらせ行為です。
場合によっては他社員から「暇そうにしている」と誤解され、二次的な被害が生まれる危険性もあります。
仕事を与えられない日々が続いた場合も、上司による嫌がらせではないかと疑うことが大切です。
プライベートの領域に踏み込んでくる
勤務外の時間やプライベートにまで嫌がらせレベルで干渉してくる上司も少なくありません。
プライベートに干渉してくる上司は、寂しさや嫉妬の感情から部下を巻き込んでしまいがちです。
部下の予定を無視してお酒の席に連れ回したり、恋愛や結婚の話題を頻繁に出してきたりといったパターンもあります。
上司によるプライベートへの干渉はプライバシーの侵害にあたり、いずれセクハラやモラハラに発展する危険性もあるでしょう。
上司による嫌がらせが起こるのはなぜ?考えられる原因を解説
上司による嫌がらせが起こる背景には、下記の原因があると考えられます。
- 自己愛や自己顕示欲が強い
- 支配欲により自分に従わせたい
- 完璧主義なところがある
- 空気が読めない
- 他責思考が強く自身の自覚がない
- 共感力の低さにより事の重大さに気づけない
- 前上司のやり方を真似している
- 妬み・嫉妬による嫌がらせをしている
それぞれの原因に潜む心理的な要素も紹介します。
自分の上司に当てはまるパターンを見つけ、考えられる原因を考察するうえでの参考にしてください。
自己愛や自己顕示欲が強い
嫌がらせをしてくる上司は、自己愛や自己顕示欲が強い性格の可能性があります。
自己肯定感の高さゆえに、自分より立場が下の人間を無碍に扱ってしまうパターンです。
「自分は正しい」という思い込みのもと、部下に対して平気で侮辱行為をしてしまう上司は決して少なくありません。
上司から侮辱的管理を受けた部下は、仕事のパフォーマンスや成果が上がりにくくなるといった研究結果も出ています。
参考:細見 正樹 (兵庫県立大学政策科学研究所客員研究員)「上司の侮辱的管理がもたらす影響」
萎縮した部下は積極的に意見を出さなくなり、創造性や協働性が損なわれてしまうでしょう。
自己愛の強い上司は批判を受け入れにくく、自分の行為がハラスメントにあたる自覚が乏しいことも特徴です。
支配欲により自分に従わせたい
「部下=自分より下の存在」という支配欲により、嫌がらせ行為をしてくる人も一定数います。
支配欲の強い上司は仕事の成果を出すために部下を「駒」として扱ってしまう傾向があります。
部下は常に自分に従うべきものだと思い込んでいる上司は、稼働状況やプライベートに関わらず、無理な要求を押し付けがちです。
心理学的論文によると、成果を出すために支配的なふるまいを見せる上司も一定数いると記載されています。
参考:チャナ・R・ショーンバーガー Chana R. Schoenberger(アメリカの業界紙 American Banker編集長)「支配型リーダーがチームワークを阻害する」
上司の在り方に明確な正解はないものの、支配欲の強い人の下で働けないと感じた場合は環境を変える必要もあるでしょう。
完璧主義なところがある
「こうでなければいけない」といった完璧主義により、無意識に部下へ嫌がらせをしてしまう人も少なくありません。
自らに対して高いハードルを課す一方で、部下に対しても自分の「当たり前」レベルを求める上司は、完璧主義の可能性が高いです。
ある論文では、完璧主義な上司は責任感が非常に強く、自分や部下に対しても高い基準を求める傾向があると記載されています。
参考:林 久美子(早稲田大学)「上司−部下間の類似性認知が部下の対人魅力および職務満足に与える影響」
あえて厳しい環境で学びたい方には合っているかもしれない反面、時には上司の完璧主義から自分の身を守る行動も大切です。
空気が読めない
嫌がらせをしてくる上司の中には、単純に空気を読めない人もいます。
空気の読めない上司は、職場での立場に関わらず、人間関係の構築があまり上手にできません。
仕事において意見の対立や批判を受けると、反射的に上司の立場を利用して周囲の意見を聞き入れない人もいます。
ここで怖いのが、空気の読めなさゆえに部下の成果や行為を侮辱してしまい、精神的に追い詰めてしまうといったケースです。
心理学的論文では、上司による振る舞い次第で部下の仕事におけるパフォーマンスにも変化が生じると記載されています。
参考:細見 正樹 (兵庫県立大学政策科学研究所客員研究員)「上司の侮辱的管理がもたらす影響」
上司と会話する中で「空気が読めない人なのでは?」と感じたら、今後嫌がらせレベルの行為をしてこないか警戒しましょう。
他責思考が強く自身の自覚がない
上司の中には他責思考により、部下への嫌がらせを自覚しないケースがあります。
「部下の能力不足が悪い」などといって自身の振る舞いを正当化し、嫌がらせ行為をあくまで指導の一環と位置づけてしまうのです。
こうした上司は自分の言動によって部下が傷ついている事実を認めず、原因を常に相手に押し付ける傾向があります。
他責思考の強い上司のもとに配属された場合、反論すればするほどより酷い嫌がらせを受ける可能性も否定できません。
上司独自の解釈を展開され「話が通じない」と感じたら、被害が深刻になる前に打つ手を考える必要があるでしょう。
共感力の低さにより事の重大さに気づけない
共感力が乏しく、無意識のうちに部下へ侮辱的な発言をしてしまうことに気付けない上司もいます。
心理学的論文によると、上司の侮辱的な発言はたとえ無意識であっても部下の仕事に支障をきたすと記載されています。
参考:細見 正樹 (兵庫県立大学政策科学研究所客員研究員)「上司の侮辱的管理がもたらす影響」
嫌な言動を繰り返してくる上司は、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)の可能性があります。
悪気なく失言や侮辱を繰り返す上司にあたったら、精神疾患の可能性も疑いましょう。
前上司のやり方を真似している
嫌がらせをしてくる上司の中には、自分が過去に上司から受けてきた「仕打ち」をそのまま真似ているケースもあります。
特に体育会系の部活出身者の場合、学生時代から培われた「縦社会」の意識が心の底に根付いているケースも珍しくありません。
このパターンに該当する上司は、昔の上司から受けてきた行為を「今度は自分がする番だ」と考えがちです。
上司と会話する機会がある場合、一般社員時代の話を聞いてみるのも良いでしょう。
妬み・嫉妬による嫌がらせをしている
部下への妬みや嫉妬により、嫌がらせをしてくる上司も少なからずいます。
上司による嫉妬の原因は、人生の充実度や職場での待遇など様々です。
部下に対する羨ましさゆえに嫌がらせをしてくるため、対処法を考えるのは簡単ではありません。
ある論文では、上司による嫉妬の感情は下記の事象につながる危険性が示唆されています。
- 従業員同士の協力やスキルアップの阻害
- 非難・監視・攻撃的な態度といった行動
- 組織全体におけるパフォーマンスの低下
上司の嫉妬により嫌がらせを受けている場合、転職や異動など環境を変える選択肢も検討しましょう。
上司の嫌がらせへの対処法まとめ|種類別に解説
上司の嫌がらせに対処するには、下記4つの方法がおすすめです。
方法ごとのメリット・デメリットも紹介します。
自分の受けている嫌がらせや置かれている立場から、ベストな方法を選択しましょう。
信頼できる先輩や同僚に相談する
上司による嫌がらせに悩んでいる方は、まず信頼できる先輩や同僚に相談してください。
特定の上司による嫌がらせなら、同様の悩みを抱えている人が他にもいる可能性があります。
場合によっては他の先輩や過去に同等の経験をした同僚など、強い味方を作れるかもしれません。
しかし、相談相手を間違えてしまうと本人に告げ口されてしまい、嫌がらせがエスカレートしてしまう危険性もあります。
社内に信頼できる相談相手がいない場合、社内外における窓口への相談も視野に入れましょう。
社内外の窓口を活用する
上司の嫌がらせによる悩みを解決したい場合、総務部やハラスメント相談窓口など社内の窓口への相談も検討しましょう。
社内の窓口へ相談すると、上司の嫌がらせを「個人的な問題」ではなく「組織の課題」として取り扱ってもらえる可能性があります。
なお、社内の窓口が存在しない(または機能していない)場合は、下記など社外の窓口を利用するのもおすすめです。
- 労基(労働基準監督署)
- 総合労働相談コーナー(都道府県労働局)
- 弁護士
- 法律相談窓口など
社内に頼れる窓口がない場合は、職場における問題解決のプロが在籍する機関を探しましょう。
思い切って転職も検討する
上司の嫌がらせによって仕事やメンタルに支障をきたしている場合、思い切って転職するのも一つの選択肢です。
転職を成功させれば上司から完全に解放され、新たな環境で仕事のリスタートを切れます。
結果次第では、同時にキャリアアップや年収アップも十分に狙えるでしょう。
ただし、転職したからといって新しい環境で上司の嫌がらせ問題を解決できる保証はありません。
場合によってはさらに悪質な上司にあたるリスクもあるため、情報収集を徹底して転職の戦略を立てる必要があります。
探偵事務所に相談する
上司の嫌がらせへの対処法がわからず悩んでいる方には、探偵事務所への相談もおすすめです。
探偵事務所には、上司による嫌がらせの根本原因調査や改善方法の提案に強みを持つプロのスタッフが在籍しています。
探偵の調査力を活用すれば、上司による嫌がらせ行為を客観的に立証しつつ、法的措置を取れる可能性もあります。
被害が深刻な場合、弁護士と連携して訴訟に踏み切る際のサポートを受けることも可能です。
転職はせずに上司の嫌がらせから解放されたい場合、探偵事務所への相談も検討しましょう。
上司の嫌がらせ対処に関する相談なら「日本総合調査事務所」へ
上司による嫌がらせは、周囲に相談しづらく、一人で抱え込んでしまいがちです。
「証拠がなく社内窓口に報告できない」「どう対処すればよいかわからない」「転職せずに問題を解決したい」という場合、探偵への相談が有力な選択肢となります。
探偵に依頼することで、以下のような支援が期待できます。
- 上司の嫌がらせ行為を客観的に記録・立証できる(メール、チャット履歴、音声記録、目撃証言など)
- 社内窓口への報告や法的措置に必要な裏付け資料を準備できる(総務部、ハラスメント相談窓口、労基、弁護士への相談時に活用)
- 上司の言動パターンや嫌がらせの原因を調査・分析できる(自己愛、支配欲、完璧主義、妬み・嫉妬など)
- 他の被害者の存在や組織的な問題を明らかにできる(個人的な問題ではなく組織の課題として扱える)
- 問題解決までの道筋を示し、法律家との連携を支援できる(訴訟に踏み切る際のサポート)
上司の嫌がらせを我慢し続けると、ストレスや心労によりメンタルに異常をきたすリスクが高まります。
エスカレートした場合、精神的な病になってしまい、仕事が続けられないまでに追い詰められることもあります。
会社の上司だからと遠慮をする必要はありません。
自分の身は自分しか守ることができません
事態が悪化する前に専門家へ相談しましょう。
「誰に相談すべきかわからない」「証拠がなく動けない」という状況なら、探偵への相談を検討してみてください。
探偵に相談すべきか迷っている方は、以下の記事を参考に判断してみてください。
上司の嫌がらせに関してよくある質問
最後に、上司の嫌がらせに関してよくある質問へ回答します。
上司の嫌がらせを我慢し続けることのリスクは?
上司による嫌がらせを我慢し続けると、ストレスや心労によりメンタルに異常をきたすリスクが高まります。
メンタルの異常が発生すると、下記の健康被害が発生しやすくなるため注意が必要です。
- 睡眠障害
- 頭痛
- 腹痛・下痢
- 謎の倦怠感
- 脱毛症
- うつ症状など
嫌がらせのレベルや期間によっては、適応障害により複数の症状が同時に現れることもあります。
ストレスによる身体の不調を感じたら、一刻も早く社内外窓口や探偵事務所へ相談しましょう。
上司の嫌がらせや職場いじめは訴えたもの勝ち?
結論、上司の嫌がらせや職場いじめは「訴えたもの勝ち」とは言い切れません。
しかし、訴訟することで問題解決への糸口を見出しやすくなります。
上司による嫌がらせを放置すると、周囲に気づかれないまま状況が悪化してしまう可能性が高まります。
自ら訴訟に向けたアクションを起こすことで、上司が今までの行いに気づくケースもあるでしょう。
今は上司による嫌がらせを受けていなくても、自分の身を守れるよう証拠の集め方や相談先を知っておくのが大事です。
パワハラに該当する言葉一覧は?
パワハラとみなされる言葉は、主に下記などがあります。
- 「お前は無能だ」
- 「給料泥棒」
- 「お前の代わりはいくらでもいる」
- 「こんなこともできないのか」
- 「存在価値がない」
- 「辞めてしまえ」など
いずれも人格否定や威圧的な表現が含まれており、業務上の指導とは大いに異なります。
上司とのメールやチャットにパワハラと思われる言葉が残っている場合、画像形式で保存すれば証拠として活用可能です。
自分が部下を持ったときも、パワハラに該当する言葉はくれぐれも使わないようにしましょう。
パワハラ上司への仕返しで言ってはいけない言葉は?
パワハラ上司への仕返しでは、下記の内容を含む発言をしないよう注意が必要です。
- 人格否定を含む内容(「あんたの方が無能だ」「生きてる価値がない」など)
- 罵倒や挑発(「やってみろ」「どうせ誰も尊敬してない」など)
- 虚偽の情報(「嫌われていることを知らないくせに」など)
- 仕返しや脅迫を示唆する言葉(「仕返ししてやる」「訴えてやる」など)
仕返しの言葉次第では、上司のさらなる怒りを買ってしまうリスクがあります。
最悪の場合、部下から上司に対する「逆パワハラ」として捉えられる可能性も否定できません。
パワハラ上司への仕返しは、感情を爆発させるのではなく、水面下で計画的に行うのが鉄則です。
人に嫌がらせをする人は病気ですか?
人に嫌がらせをしてくる人は、下記の病気である可能性があります。
- 自己愛性パーソナリティ障害
- 反社会性パーソナリティ障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- ASD(自閉スペクトラム症)
- うつ病や適応障害などからくる精神疾患など
精神的な疾患を患っている上司の場合、無意識に部下へストレスを与えてしまうケースもあります。
しかし、嫌がらせをしてくる上司の中には精神疾患を患っていないケースも珍しくありません。
「上司は病気なので嫌なことをされても仕方がない」と決めつけず、自分の身を守れる選択肢を取ることが大切です。
関連記事:足のつかない嫌がらせに悩んでいる方へ!合法的な仕返し5選
職場で幼稚な嫌がらせを受けているときの対策は?
職場で上司に幼稚な嫌がらせを受けているときは、今後の相談や訴訟に備えて証拠を記録し続ける必要があります。
くだらない嫌がらせでも、長期的に続く場合はその日に起きた事象・内容をメモしておきましょう。
メールやチャット履歴など、形に残るものは保存しておくのがおすすめです。
保存した上司による嫌がらせやパワハラの記録は、損害賠償や裁判においても役立つ材料となります。
上司の嫌がらせは周囲に相談しづらいケースもあるため、信頼できる同僚や社内窓口に伝える際の証拠として提示してください。
関連記事:職場で「幼稚な嫌がらせ」がストレス…|相手にしないべき?対処法まとめ
まとめ
上司の嫌がらせでよくあるケースは多岐にわたり、発生原因も性格や価値観によるものなど様々です。
対処方法は嫌がらせの種類や上司によって異なるため、一人で解決策を考えるのは決して簡単ではありません。
上司から嫌がらせを受けている方は、該当するケースから考えられる原因を洗い出しましょう。
考えられる原因がわかったら、信頼できる同僚や社内外の窓口を活用して解決を目指す必要があります。
解決策を見出せない場合は、日本総合調査事務所へ遠慮なくご相談ください。
日本総合調査事務所では、上司による嫌がらせやパワハラに関する相談を24時間・365日無料で承っています。
電話・メール・LINEいずれかの方法でお気軽にお問い合わせください。